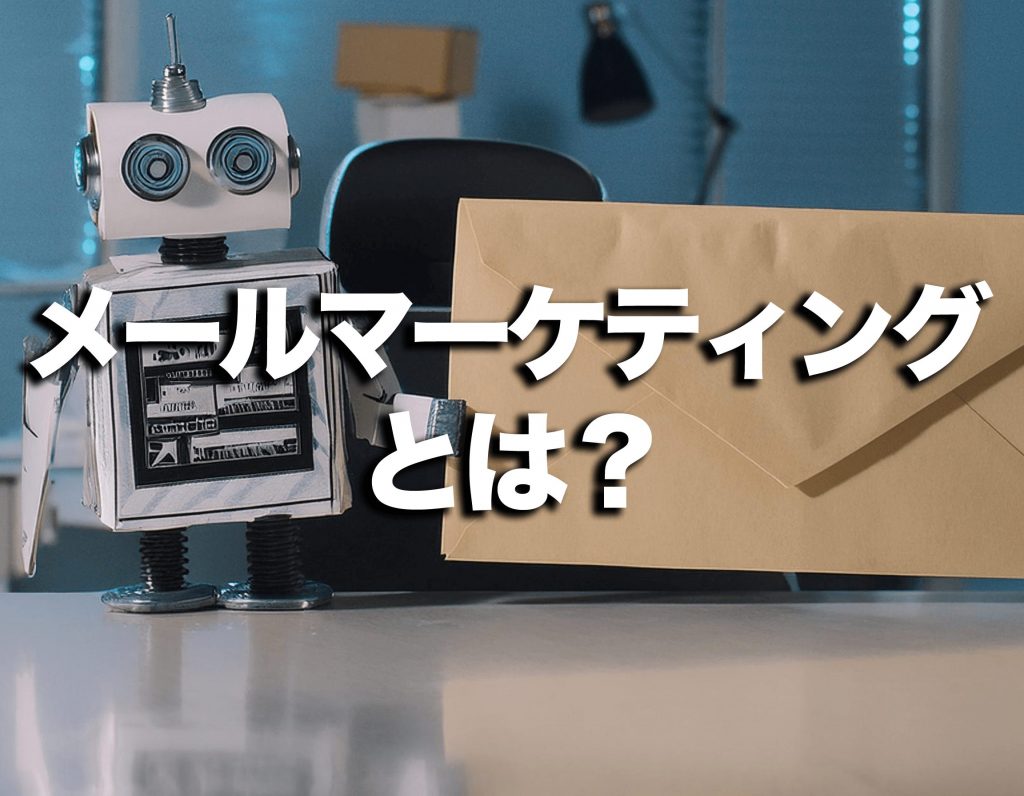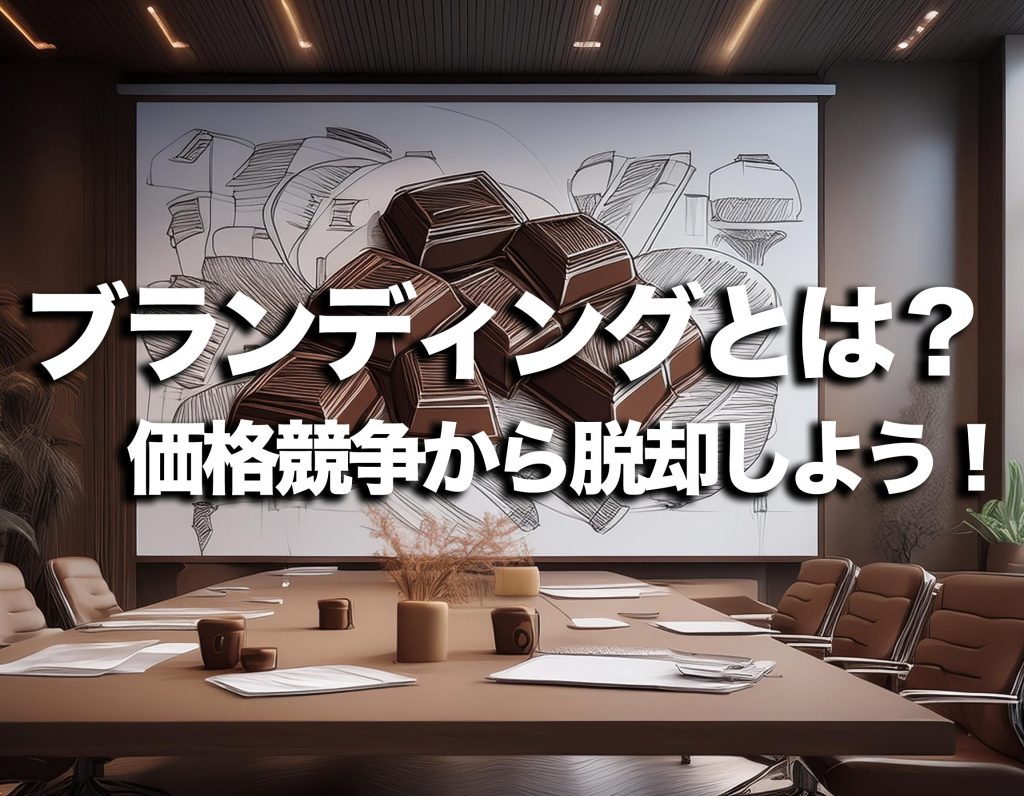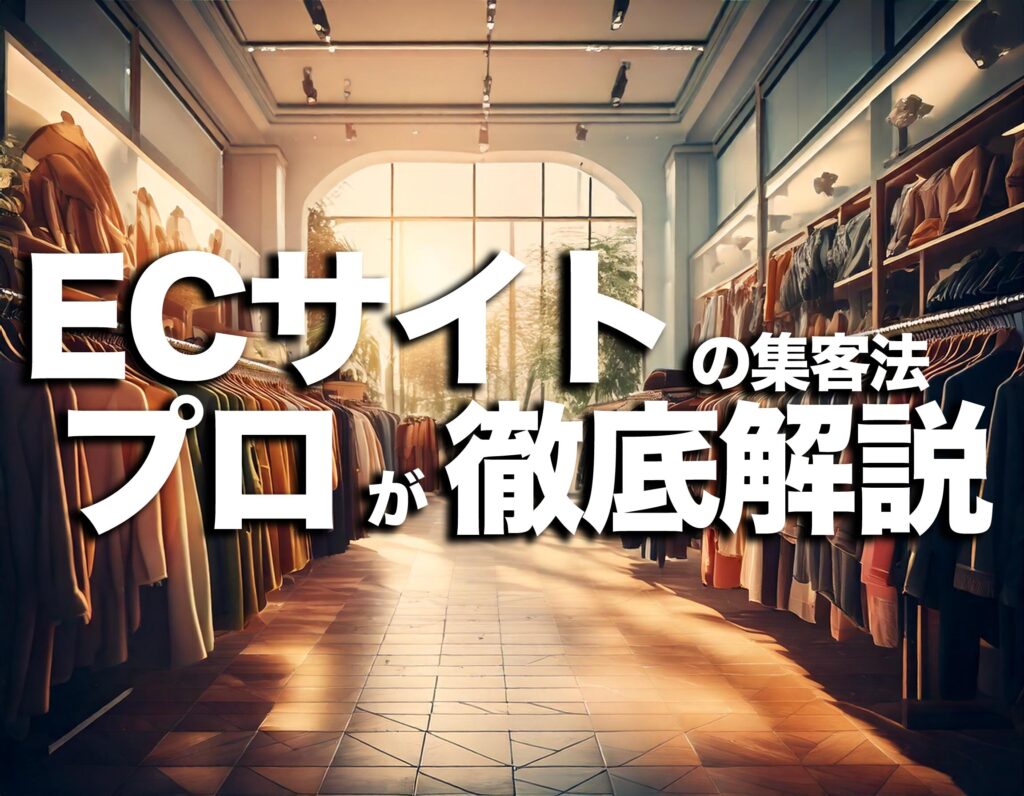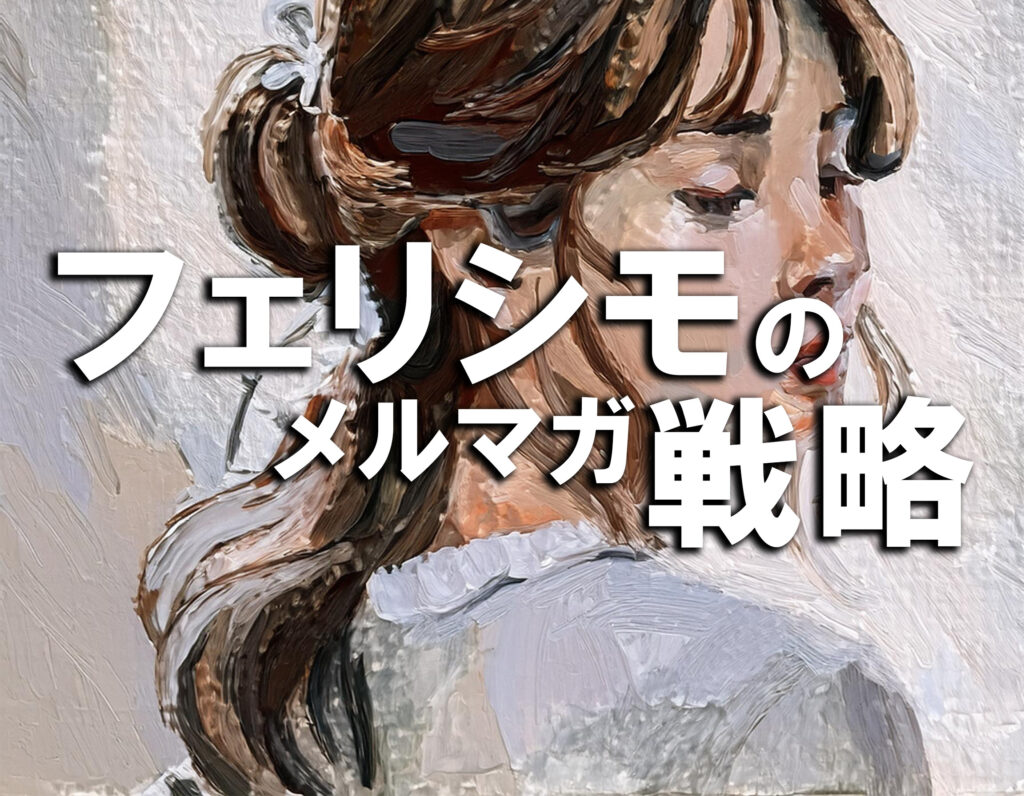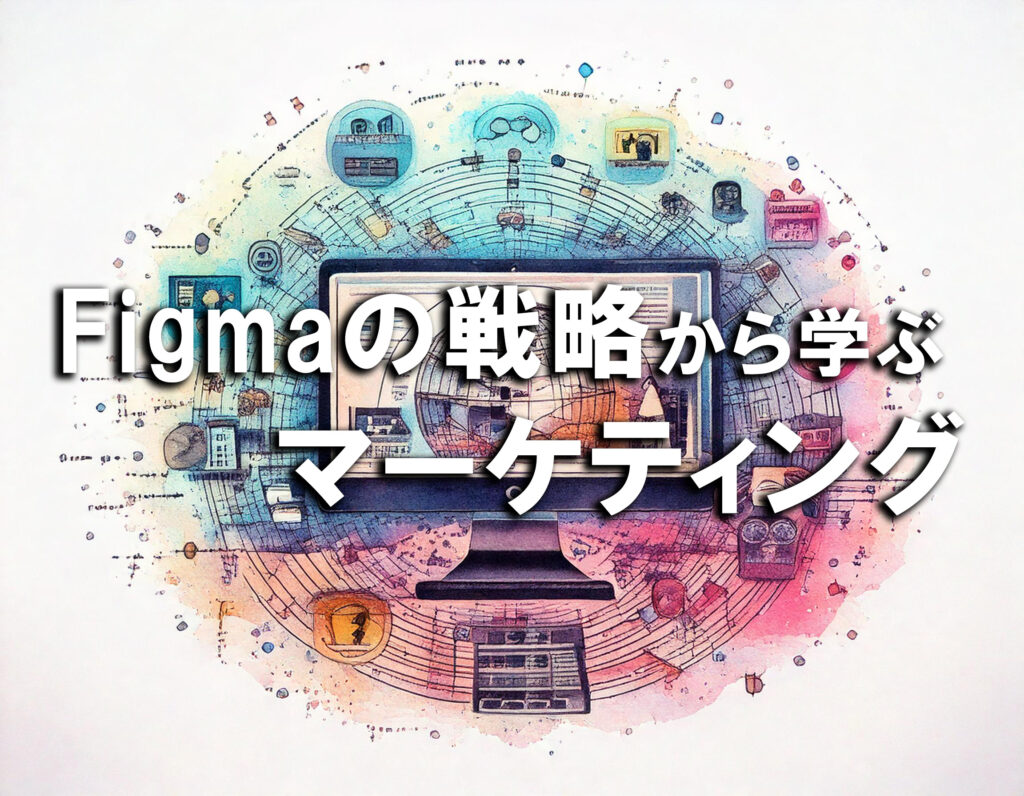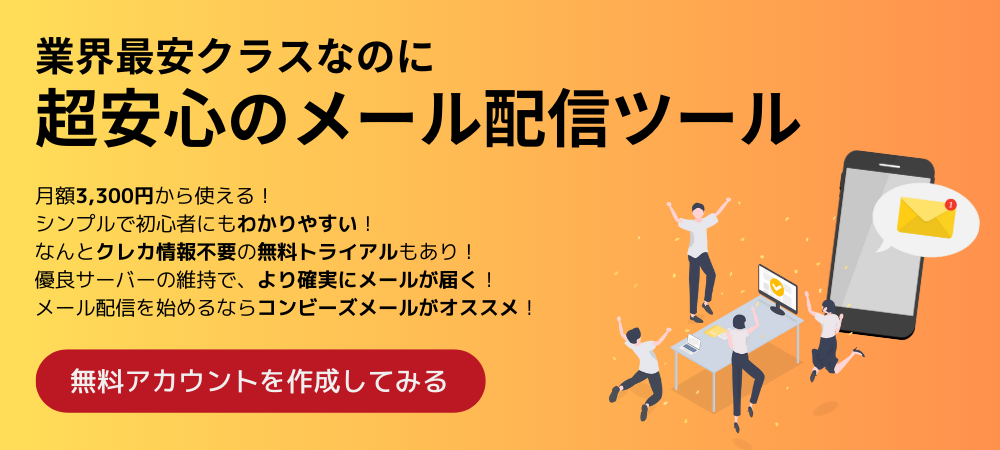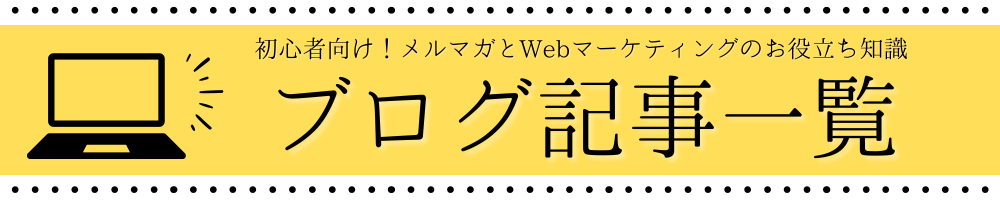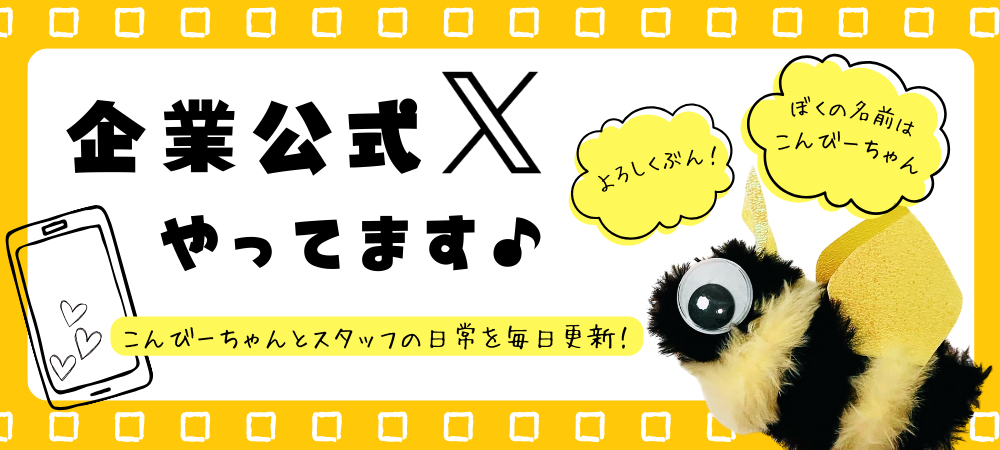フォルクスワーゲン。
その名を知らぬ者はいないほど、世界中で親しまれているドイツの自動車ブランドです。
しかし、その成功は一朝一夕に成し遂げられたものではありません。
「国民車」という原点から始まり、時代を象徴する数々の名車を生み出し、時には大胆な広告戦略で人々を驚かせ、そして今、100年に一度と言われる自動車業界の大変革期においても、未来を見据えた挑戦を続けています。
そこで今回は、フォルクスワーゲンのブランドがどのようにして築き上げられ、なぜこれほどまでに多くの人々を惹きつけるのか、その歴史、象徴的な出来事、そして未来への戦略を深掘りします。
単なる自動車メーカーの事例としてではなく、あらゆるビジネスに応用可能な普遍的なブランディングのヒントが、そこには隠されているはずです。
フォルクスワーゲンの巧みなブランド戦略から、自社のビジネスを成長させるための学びを見つけ出しましょう!
ページコンテンツ
▼しっかり届くのに、安くてシンプル。20年以上愛されているメルマガツールはこちら▼
フォルクスワーゲンの歴史
フォルクスワーゲンのブランドストーリーは、単なる自動車製造の歴史にとどまらず、時代を映し出す鏡であり、巧みな戦略と揺るぎない哲学によって築き上げられてきました。
その歩みは、まさに大衆のための車作りから始まり、幾多の困難を乗り越えながらも、世界中の人々に愛されるブランドへと成長を遂げた物語です。
ここでは、その歴史の重要な転換点や象徴的な出来事を通じて、フォルクスワーゲンのブランドがどのように形成されてきたのかを紐解いていきましょう。
“謙虚さ”が武器になった広告革命「Think Small」
参照:https://vw-dealer.jp/blog/vw_edogawa/2023/01/post-215.html
フォルクスワーゲンはナチス・ドイツの指導者であったアドルフ・ヒトラーの構想から生まれ、その設立と初期の発展においてナチス政権と深く結びついていました。
戦後はその過去を乗り越え、世界有数の自動車メーカーへと成長しましたが、その歴史的経緯は記憶されるべき重要な点です。
そして1950年代後半、フォルクスワーゲンは新たな挑戦として、小型車「ビートル」でアメリカ市場への本格参入を試みます。
当時のアメリカ市場は、大型でパワフル、かつ豪華絢爛なデザインの車が成功の象徴として人々の憧れを集めていた時代であり、そのため当初、ビートルはその小ささやユニークな形状から「奇妙な車」と見なされることも少なくありませんでした。
しかし、フォルクスワーゲンは逆境を逆手に取り、広告会社DDB(Doyle Dane Bernbach)と共に、自動車広告の歴史に名を刻む画期的なキャンペーンを展開します。
それが、1959年から始まった「Think Small」キャンペーンです。
このキャンペーンは、当時の主流とは全く異なるアプローチを採用しました。
ビートルの「小ささ」や「質素さ」を隠すのではなく、むしろそれを前面に押し出し、「小さいことは賢い選択である」という価値観を提示したのです。
例えば、広告ビジュアルでは広大な白いスペースにポツンと小さくビートルを配置し、「Think Small.(小さいことを考えよう)」という短いコピーを添えるなど、シンプルかつ大胆な表現で人々の目を引きました。
また、「Lemon(欠陥品)」と題した広告では、厳しい品質基準によって出荷されなかった一台のビートルを取り上げ、その徹底した品質管理と誠実さをアピールしました。
これらの広告は、製品の欠点とも取れる特徴をユーモラスかつ正直に語ることで、逆に消費者の信頼と共感を獲得することに成功。
派手さやステータスを求める風潮に対して、実用性や経済性、そして何よりもブランドの「正直さ」という新たな価値基準を提示し、ビートルは単なる移動手段ではなく、個性的なライフスタイルを象徴する存在として、アメリカの消費者に受け入れられていったのです。
この「Think Small」キャンペーンは、自己認識と正直さがいかにブランドに強い個性と共感を生み出すかを示す、広告史における金字塔として今も語り継がれています。
“ただの車”じゃないブランドの象徴「ビートルとゴルフ」
フォルクスワーゲンのブランドイメージを語る上で、その歴史を彩ってきた数々の名車の存在は欠かせません。
特に「ビートル」と「ゴルフ」は、単に人気車種というだけでなく、ブランドのDNAを体現し、時代を超えて多くの人々に愛され続けることで、フォルクスワーゲンの“人格”そのものを形作ってきたと言えるでしょう。
ビートル
参照:https://sp.volkswagen.co.jp/brand-history/30s-40s/
初代「ビートル(タイプ1)」は、フェルディナント・ポルシェ博士の設計思想に基づき、「国民車」として誕生しました。
前述の通り、その歴史は第二次世界大戦という困難な時代と深く結びついていますが、戦後は手頃な価格と信頼性、そして愛らしいデザインで、ヨーロッパのみならず世界中の人々の生活を支える存在となりました。
経済復興期のドイツでは、多くの家族にとって初めてのマイカーとなり、自由な移動と豊かな生活の象徴として親しまれました。
単なる移動手段を超え、オーナーにとっては家族の一員のような、あるいは親しい友人のような、温かい感情を伴う“愛される存在”として、フォルクスワーゲンのブランドの原点となったのです。
そのユニークなスタイルと堅実な性能は、ヒッピーカルチャーのアイコンとなるなど、時代を象徴する文化的な現象も生み出しました。
ゴルフ
一方、1974年に登場した「ゴルフ」は、ビートルが築き上げた「大衆のための実用車」というDNAを受け継ぎつつ、FF(前輪駆動)レイアウトやハッチバックスタイルといった、より現代的で合理的な設計を取り入れました。
参照:https://www.volkswagen.co.jp/ja/magazine/golf_journal.html
初代ゴルフは、その卓越したパッケージングによる広い室内空間、きびきびとした走行性能、そして飽きのこない洗練されたデザインが高く評価され、瞬く間に世界的なベストセラーとなります。
「実用性」「デザイン」「走りの楽しさ」という、車に求められる基本的な要素を高次元でバランスさせたゴルフは、コンパクトカーの新たなベンチマークとなり、その後の自動車設計に大きな影響を与えました。
世代を重ねるごとに進化を続けながらも、常にその時代のニーズに応える実用性と信頼性を提供し続けることで、ゴルフはフォルクスワーゲンブランドの中核を担うモデルとして確固たる地位を築き上げました。
ビートルとゴルフ、この2台の名車が半世紀以上にわたって積み重ねてきた実績と、それに伴う顧客からの揺るぎない信頼こそが、今日のフォルクスワーゲンブランドの“人格”を形成する上で最も重要な要素と言えるでしょう。
変わらぬロゴと変化を恐れない姿勢
参照:https://www.vw-okayama.com/staffblog/2024/10/24/12059
企業やブランドの顔とも言えるロゴマークは、その理念や価値観を視覚的に伝える重要な役割を担います。
フォルクスワーゲンの「VW」を組み合わせた円形のロゴもまた、その歴史の中で幾度かのデザイン変更を経ながらも、ブランドの核となるメッセージを発信し続けてきました。
初期のロゴは、ナチス・ドイツ時代のドイツ労働戦線(DAF)の歯車とハーケンクロイツを組み合わせたものでしたが、戦後、イギリス軍管理下で再建される際に歯車のデザインが簡略化され、現在の円の中に「V」と「W」を配置する基本的な形が確立されました。
その後も、時代のデザイントレンドや企業戦略の変化に合わせて、ロゴは細かなリファインが繰り返されてきました。
例えば、文字の太さや円の縁取り、カラーリングなどが変更されてきましたが、中心にある「V」と「W」の組み合わせという核心的な要素は一貫して保たれています。
これは、フォルクスワーゲンが大切にしてきた「大衆のための車」という基本理念や、品質へのこだわり、そして顧客からの「信頼」といった、ブランドの普遍的な価値が変わらないことを象徴していると言えるでしょう。
近年では、2019年に発表された新しいロゴデザインが記憶に新しいところです。この変更では、立体的な表現からフラットデザインへと移行し、よりシンプルでモダンな印象を与えるものとなりました。
参照:https://www.vw-dealer.jp/blog/vw_ikegami/2020/06/post-637.html
これは、電動化やデジタル化といった自動車業界の大変革期において、フォルクスワーゲンが未来に向けて変化を恐れずに進んでいくという「革新」への強い意志を示すものです。
このように、フォルクスワーゲンのロゴは、その時代ごとの変化を柔軟に受け入れつつも、ブランドの根幹となる「変わらない信頼」と、常に進化を続ける「変わり続ける革新」という二つの側面を巧みに表現する象徴として機能しているのです。
▼しっかり届くのに、安くてシンプル。20年以上愛されているメルマガツールはこちら▼
フォルクスワーゲンのブランド戦略
フォルクスワーゲンは、その長い歴史の中で培ってきた信頼と革新性を基盤に、未来のモビリティ社会を見据えた野心的なブランド戦略を展開しています。
自動車業界が100年に一度の大変革期を迎える中、伝統的な自動車メーカーから、持続可能でユーザー中心のモビリティを提供するテクノロジー企業へと舵を切ろうとしています。
ここでは、その変革を牽引するビジョン、具体的な行動指針、そしてブランド哲学の進化について掘り下げていきます。
未来を見据えた大きなビジョン「Mobility for Generations」
フォルクスワーゲンが掲げる「Mobility for Generations(世代のためのモビリティ)」というビジョンは、単に次世代の自動車を開発するという短期的な目標にとどまりません。
それは、将来の世代に至るまで持続可能で、かつ豊かな移動体験を提供することを目指す、長期的かつ包括的な取り組みです。
このビジョンの核心には、自動運転技術の進化、電動化へのシフト、そしてソフトウェアを核とした車両機能の高度化という3つの大きな柱が存在します。
これらを通じて、フォルクスワーゲンは伝統的な「クルマを作る会社」から、革新的な「モビリティのテック企業」へと自らを変革しようとしています。
この変革は、人々の生活における「移動」そのものの概念をアップデートすることを意味します。
例えば、
| 電動化:環境負荷の低減に貢献するだけでなく、静かでスムーズな移動体験や、新たな車両デザインの可能性を広げます。 高度な自動運転技術:運転の負担を軽減し、車内での時間をより自由に、そして有意義に活用できるようにすることを目指しています。 ソフトウェアの向上:車両の機能を常に最新の状態に保ち、個々のユーザーのニーズに合わせたカスタマイズや新しいサービスを提供するための基盤となります。 |
この壮大なビジョンは、企業としての社会的責任を果たしつつ、新たな成長機会を創出するための羅針盤となっています。
2030年に向けた行動指針「NEW AUTO」戦略
フォルクスワーゲングループが2021年に発表した「NEW AUTO」戦略は、2030年を見据えた具体的な行動指針であり、前述の「Mobility for Generations」というビジョンを実現するためのロードマップと言えます。
この戦略の中心には、自動車産業の構造変化に対応し、収益性の高い持続的な成長を確保するための明確なコミットメントが示されています。
電気自動車(EV)への本格的な移行
その具体的な柱として、まず電気自動車(EV)への本格的な移行が挙げられます。
「ID.ファミリー」に代表されるEV専用プラットフォームを開発し、魅力的なモデルラインナップを拡充することで、2030年までにグループ全体でのEV販売比率を大幅に引き上げる目標を掲げています。
バッテリー技術と充電インフラへの大規模な投資
次に重要なのが、バッテリー技術と充電インフラへの大規模な投資です。
バッテリーセルに関しては、内製化を進めるとともに、ヨーロッパに複数のギガファクトリーを建設する計画を発表しており、安定的な供給体制とコスト競争力の強化を目指しています。
ソフトウェア開発能力の強化
また、ソフトウェア開発能力の強化も不可欠です。
グループ内のソフトウェア開発部門「CARIAD(カリアド)」を通じて、車両OSやクラウドプラットフォーム、自動運転技術などの開発を内製化し、デジタルサービスによる新たな収益源の確立を目指しています。
さらに、自動運転技術の開発を推進し、将来的にはMaaS(Mobility as a Service)分野への本格参入も視野に入れています。
MaaS(Mobility as a Service)とは、複数の交通手段をITで統合し、利用者が検索から予約、決済までを一つのサービスとしてシームレスに行えるようにする、移動の利便性を高める概念です。自動運転技術との融合により、さらに革新的な移動サービスが登場する可能性を秘めています。
このように、「NEW AUTO」戦略は、電動化、ソフトウェア、バッテリー、モビリティサービスという未来の自動車産業を構成する主要な要素を網羅し、フォルクスワーゲンが未来においてもリーディングカンパニーであり続けるための具体的な道筋を描き出しています。
(※リーディングカンパニーとは、特定の業界や市場で主導的な地位にあり、技術革新やトレンド創出などで他社に先駆けて業界全体を牽引する影響力を持つ企業のこと。)
スローガンは「Das Auto」から「Moving People Forward」へ
ブランドスローガンは、企業が顧客や社会に対して発信するメッセージの核心であり、その時代におけるブランドの姿勢や目指す方向性を端的に示すものです。
フォルクスワーゲンは長年、「Das Auto.(ザ・カー、これぞ自動車の意)」というスローガンを掲げ、ドイツのエンジニアリング力に裏打ちされた品質と信頼性を訴求してきました。
このスローガンは、製品そのものの優秀さ、つまり「モノ」を中心としたブランドの自信を象徴するものでした。
参照:https://www.volkswagen.co.jp/ja/magazine/e-factory.html
しかし、自動車業界を取り巻く環境が大きく変化し、顧客の価値観も多様化する中で、フォルクスワーゲンはブランドのあり方を見つめ直します。
そして、近年では特定の包括的なスローガンを強く打ち出すよりも、より人間的な側面や社会との関わりを重視するコミュニケーションへとシフトしています。
かつて、「Moving People Forward(人々を前進させる)」という言葉も、フォルクスワーゲングループのイベントなどで未来への方向性を示す際に用いられたことがあり、これはまさに製品中心の考え方から、「人」を主役にしたブランドへと進化しようとする姿勢の表れと言えます。
自動車が単なる移動手段ではなく、人々の生活を豊かにし、社会をより良い方向へ動かすためのツールであるという認識が根底にあります。
この変化は、環境意識の高まり、デジタル化の進展、所有から利用へという価値観の変化など、現代社会のメガトレンドに対応しようとするブランドの意思を反映したものです。
製品の機能や性能を語るだけでなく、その製品が人々の生活や社会にどのような価値をもたらすのか、そして顧客一人ひとりの感情や体験に寄り添い、共感を呼ぶコミュニケーションを重視する。
このような姿勢の変化は、フォルクスワーゲンがこれからも時代と共に進化し、顧客とのより深いつながりを築いていこうとする決意を示しています。
詳しくは後の章、「人の記憶に寄り添うLove Brand戦略」で解説します!
まだまだある!フォルクスワーゲンの魅力的な施策
フォルクスワーゲンのブランド戦略は、壮大なビジョンや具体的な行動指針に留まらず、日々のマーケティング活動や顧客とのコミュニケーションにおいても、その魅力を多角的に発信し続けています。
環境への配慮から、新しい時代の「国民車」の提案、そして顧客との感情的な絆を深める取り組みまで、ここではフォルクスワーゲンが展開する注目すべき施策の数々を紹介します。
これらの施策は、ブランドの価値観を具体的に伝え、顧客との間に強いエンゲージメントを築く上で重要な役割を果たしています。
サステナブルなブランドへの挑戦「Way to Zero」
参照:https://sp.volkswagen.co.jp/way-to-zero/
地球環境への配慮は、現代の企業にとって避けては通れない重要な課題です。
フォルクスワーゲンは、この課題に対して「Way to Zero」という明確な脱炭素化戦略を掲げ、持続可能なモビリティの実現に向けた具体的な取り組みを加速させています。
この戦略の最終目標は、2050年までに製品ライフサイクル全体でカーボンニュートラルを達成すること。
これは単に電気自動車を増やすといった一部分の取り組みではなく、車両の電動化はもちろんのこと、生産プロセスにおける再生可能エネルギーの利用拡大、さらには部品調達から始まるサプライチェーン全体に至るまで、事業活動のあらゆる側面でCO2排出量の削減を目指す、極めて包括的で“本気の取り組み”です。
具体的には、電気自動車「ID.ファミリー」のラインナップ拡充とグローバル展開を積極的に進めると同時に、生産工場におけるエネルギー効率の改善や、グリーン電力の導入を推進しています。
例えば、ドイツのツヴィッカウ工場は、ヨーロッパで初めて完全にカーボンニュートラルな電気自動車工場へと転換されました。
さらに、サプライヤーに対しても持続可能性基準の遵守を求め、バリューチェーン全体での環境負荷低減を図っています。
また、使用済みバッテリーのリサイクル技術開発や、持続可能な素材の活用など、資源循環型経済への移行も視野に入れた取り組みを進めています。
フォルクスワーゲンが「Way to Zero」を通じて示しているのは、環境責任を真摯に受け止め、未来世代のために具体的な行動を起こすという強い意志であり、これがブランドの信頼性と先進性を高める重要な要素となっています。
この真摯な姿勢は、環境意識の高い顧客からの共感を呼び、長期的なブランド価値の向上に貢献することが期待されます。
新しい「ピープルズカー」の形「ID.シリーズ」
かつて「ビートル」が多くの人々の生活に寄り添い、「ピープルズカー(国民車)」としての地位を確立したように、フォルクスワーゲンは電気自動車の時代においても、再び“みんなのための車”を提案しようとしています。
その象徴となるのが、電気自動車専用プラットフォーム「MEB(モジュラー・エレクトリックドライブ・マトリックス)」をベースに開発された「ID.シリーズ」です。
前の章でもご紹介した「ID.ファミリー」とも呼ばれるこのシリーズは、サステナビリティと革新的なテクノロジー、そして人々のライフスタイルに寄り添うデザインを融合させ、新しい時代の「ピープルズカー」のあり方を再定義することを目指しています。
例えば、コンパクトSUVの「ID.4」は、実用的なサイズ感と十分な航続距離、そして直感的な操作性を兼ね備え、ファミリー層や日常的に車を利用する幅広い層に向けたモデルとして開発されました。
参照:https://www.volkswagen.co.jp/ja/models/id4.html
一方、往年の名車「タイプ2(通称:ワーゲンバス)」を彷彿とさせるデザインで注目を集める「ID. Buzz」は、そのユニークなスタイリングと広々とした室内空間で、レジャーやビジネスシーンでの新たな可能性を提案しています。
これらのモデルは、単に排出ガスを出さないという環境性能だけでなく、デジタル化されたインターフェースや先進的な運転支援システムなど、未来の移動体験を感じさせる機能を備えています。
フォルクスワーゲンは、ID.シリーズを通じて、かつてのビートルがそうであったように、単なる移動手段ではなく、人々の生活に彩りを与え、世代を超えて愛される新たな時代の象徴を生み出そうとしています。
それは、最先端の技術を手頃な価格で提供し、より多くの人々に電気自動車のメリットを享受してもらうという、フォルクスワーゲンが長年培ってきた「民主化」の精神を電気自動車の時代においても継承していく試みと言えるでしょう。
人の記憶に寄り添う「Love Brand」戦略
現代の消費者は、製品の機能やスペックだけでなく、ブランドが持つストーリーや価値観、そしてそこから生まれる感情的なつながりを重視する傾向にあります。
フォルクスワーゲンは、このような消費者のインサイトに応えるべく、「Love Brand(愛されるブランド)」としての地位を確固たるものにするための戦略を積極的に展開しています。
その核心にあるのは、ブランドの豊かな歴史やヘリテージ(遺産)を大切にしながらも、常に未来を見据えた革新性を追求し、顧客一人ひとりの記憶や感情に深く寄り添うコミュニケーションです。
その象徴的な例として、過去の広告キャンペーンやアイコニックなモデルを現代的な視点で再解釈し、懐かしさと新しさを融合させたコミュニケーションが挙げられます。
例えば、特定のキャンペーン名に言及せずとも、往年の名車が登場するCMや、家族の成長と共にあり続けるフォルクスワーゲン車を描くストーリーは、多くの人の心に温かい感情を呼び起こします。
これは、単にノスタルジーに訴えかけるだけでなく、ブランドが長年にわたり人々の生活の一部であり続けてきたという事実を再認識させ、信頼感と親近感を醸成する効果があります。
フォルクスワーゲンは、スペック競争に終始するのではなく、車がもたらす移動の喜び、家族や友人との大切な時間、そして人生の様々なシーンに「フォルクスワーゲンという存在が寄り添っている」というメッセージを発信し続けています。
このような感情的なつながりを重視するアプローチは、顧客ロイヤルティを高め、ブランドを単なる工業製品ではなく、人生のパートナーのような存在へと昇華させることを目指しています。
アプローチの例を説明して行きます!
ブランドの魅力を発信!「フォルクスワーゲンマガジン」
参照:https://www.volkswagen.co.jp/ja/magazine.html
企業が自ら情報を発信するオウンドメディアは、ブランドの世界観を深く伝え、顧客との継続的な関係を築く上で非常に有効な手段です。
フォルクスワーゲンもまた、「フォルクスワーゲンマガジン」を通じて、ブランドの多岐にわたる魅力を積極的に発信しています。
このオンラインプラットフォームは、単に新製品の情報を掲載する場に留まらず、ブランドが持つストーリーや価値観、そして最新の取り組みを多角的に紹介する、いわばブランドの“編集部”のような役割を担っています。
提供されるコンテンツは実に多彩です。最新モデルの詳細な情報や開発秘話はもちろんのこと、世界各国で実施されているキャンペーンやイベントのレポート、ブランドの歴史を紐解く読み物、さらにはデザインやテクノロジーに関する専門家のインタビュー記事なども掲載されています。
特に、美しい写真や動画を駆使したコンテンツは、読者の視覚に訴えかけ、ブランドの世界観を直感的に伝えるのに効果的です。
例えば、新型車の魅力を伝えるカーレビュー動画では、走行性能だけでなく、ライフスタイルの中での活用シーンを提案することで、顧客がその車と共にある生活を具体的にイメージできるように工夫されています。
参照:https://www.volkswagen.co.jp/ja/magazine/car_review.html
このようなオウンドメディア戦略は、顧客に対して一方的に情報を押し付けるのではなく、有益で興味深いコンテンツを提供することで、自然な形でブランドへの関心を高め、理解を深めてもらうことを目的としています。
結果として、既存顧客のロイヤルティ向上に繋がるだけでなく、潜在顧客に対してもブランドの魅力を効果的に伝え、将来的な購買意欲の醸成に貢献します。
また、顧客がブランドストーリーに触れることで、製品への愛着が増し、長期的なファンを育てる基盤となるのです。
店舗ごとに情報発信!「スタッフブログ」
参照:https://www.vw-dealer.jp/blog/vw_sendai_minami/2025/04/post.html
フォルクスワーゲンのブランド戦略において、顧客との接点を強化し、親近感を醸成する上で重要な役割を担っているのが、各店舗が運営する「スタッフブログ」です。
この取り組みは、単なる製品情報の発信に留まらず、ブランドの人間味を伝え、顧客との継続的な関係構築を目指すものです。
多くのフォルクスワーゲンディーラーでは、店舗の日常やイベント情報、新型車の紹介、地域の話題などを、それぞれのスタッフが個性豊かに発信しています。
これにより、画一的な企業からのメッセージとは異なり、店舗ごとの雰囲気やスタッフの人柄が伝わりやすくなります。
例えば、ある店舗では、店長がフォルクスワーゲンの歴史を発信したり、営業スタッフが実際に新型車で1日都内をドライブした感想を写真満載で投稿するなど、内容は多岐にわたります。
参照:https://www.vw-dealer.jp/blog/vw_sendai_minami/2025/04/post.html
参照:https://www.vw-dealer.jp/blog/vw_edogawa/2024/04/id4-6.html
このような現場からのリアルな声は、顧客にとってフォルクスワーゲンブランドをより身近に感じさせ、信頼感を高める効果があります。
特に、高額な買い物である自動車の購入においては、製品の魅力だけでなく、販売店の雰囲気やスタッフの対応も重要な判断材料となります。
スタッフブログを通じて、店舗の透明性を高め、顧客が安心して来店できるような環境づくりに貢献していると言えるでしょう。
さらに、スタッフブログは、フォルクスワーゲンが大切にする「人を中心とした」ブランド哲学を体現するものでもあります。
車を販売するだけでなく、顧客一人ひとりのカーライフに寄り添う姿勢を示すことで、長期的な顧客ロイヤルティの育成に繋がります。
これは、大衆車でありながら、品質へのこだわりと人間的な温かみを両立させるフォルクスワーゲンのブランドイメージを、草の根レベルで支える重要な施策の一つと言えるでしょう。
他業種の企業が顧客とのエンゲージメントを高める上でも参考になる事例です。
▼しっかり届くのに、安くてシンプル。20年以上愛されているメルマガツールはこちら▼
フォルクスワーゲン流!ブランディング実践の3ステップ
フォルクスワーゲンの長年にわたるブランド構築の歴史と戦略は、他の業界のマーケティング担当者にとっても多くの示唆を与えてくれます。
時代を超えて愛され、信頼されるブランドをいかにして築き上げるか。
その普遍的な法則を、フォルクスワーゲンの実践から学び、自社のブランド戦略に応用するための具体的なステップとして整理してみましょう。
ここでは、そのエッセンスを3つのステップに凝縮して解説します!
ステップ1:「自社の原点」を見つめ直す
強力なブランドを構築するための最初のステップは、自社が何のために存在するのか、その根本的な価値観、つまり「原点」を深く見つめ直すことから始まります。
フォルクスワーゲンに目を向けると、その歴史は「みんなのためのクルマ(ピープルズカー)」という明確な哲学からスタートしました。
この思想は、初代ビートルから今日のID.シリーズに至るまで、形を変えながらも一貫して受け継がれています。
それは、高品質で信頼性が高く、多くの人々にとって手の届く移動手段を提供するという約束であり、ブランドのあらゆる活動の基盤となっています。
同様に、どのような企業にも、創業時に抱いた志や、時代の変化の中でも変わらず大切にしてきた独自の価値観が必ず存在するはずです。
それは、製品やサービスの品質へのこだわりかもしれませんし、顧客に対する誠実な姿勢、あるいは社会貢献への情熱かもしれません。
まずは、その企業独自の「らしさ」の源泉となっている価値観を明確に言語化することが不可欠です。
この原点を明確にすることで、ブランドの目指すべき方向性が定まり、社内外に対するメッセージにも一貫性が生まれます。
流行に左右されることなく、長期的な視点でブランドを育成していくためには、この揺るぎない「原点」こそが最も重要な羅針盤となるのです。
この原点が明確であればあるほど、その後のブランド戦略はブレることなく、力強く展開していくことができるでしょう。
ステップ2:「物語」を語る
製品やサービスが溢れる現代において、顧客の心を掴み、記憶に残り続けるブランドを構築するためには、単に機能や利便性を訴求するだけでは不十分です。
そこで重要になるのが、「物語(ストーリーテリング)」の力です。
フォルクスワーゲンのビートルやゴルフが、単なる移動手段を超えて多くの人々に愛され、文化的なアイコンにまでなった背景には、それぞれが持つ豊かな物語が存在します。
ビートルであれば、戦後の復興期における人々の希望や自由の象徴としての物語。
ゴルフであれば、実用性と運転の楽しさを両立させ、コンパクトカーの概念を塗り替えた革新の物語などです。
これらの物語が、製品に特別な意味を与え、人々の感情に深く訴えかけてきました。
企業が自社のブランドを語る際にも、このストーリーテリングは極めて有効な手法です。
例えば、
| ・創業者がどのような想いで事業を立ち上げたのか ・開発チームが困難を乗り越えて製品を生み出したエピソード ・ブランドが顧客の人生のどのような瞬間に寄り添ってきたのか |
といった物語は、事実を伝えるだけでなく、聞く人の感情を揺さぶり、共感や親近感を生み出します。
企業が大切にしている信念や哲学も、具体的なエピソードを通じて語られることで、より深く顧客に伝わるでしょう。
物語は、ブランドに人間味を与え、顧客との間に感情的な絆を築くための強力な触媒となります。
スペックだけでは伝えきれないブランドの価値や個性を、魅力的な物語に乗せて発信することが、記憶に残るブランドへの道筋となるのです。
ステップ3:あらゆる接点で「一貫性」を保つ
ブランドの「原点」を明確にし、それを魅力的な「物語」として語る準備ができたら、次に取り組むべきは、顧客がブランドと接触するあらゆるポイントで、そのメッセージや世界観を一貫して体験できるようにすることです。
フォルクスワーゲンが長年にわたり築き上げてきた強固なブランドイメージは、まさにこの「一貫性」の賜物と言えるでしょう。
例えば、シンプルでありながら信頼性と親しみやすさを感じさせる「VW」のロゴマークは、時代に合わせてリファインされつつも、その核となる印象は変わらずに受け継がれています。
広告コミュニケーションにおいても、「Think Small」のような歴史的なキャンペーンから近年のものまで、ユーモアや人間味を感じさせるトーン&マナーが貫かれています。
この一貫性は、ロゴや広告といった目に見える要素だけでなく、製品デザインの細部、ディーラーでの接客応対、ウェブサイトの使いやすさ、さらにはコールセンターの対応や送られてくるメールマガジンの文面に至るまで、顧客がブランドと触れる可能性のあるすべてのタッチポイントで意識されなければなりません。
どこで、どのようにブランドに接触しても、そこから感じ取れる印象や価値観が統一されていること。
これが、顧客の中に明確で揺るぎないブランドの“人格”を形成し、安心感と信頼感をもたらします。
「あのブランドらしいな」と自然に感じてもらえる状態を創り出すことができれば、顧客はブランドに対してより深い愛着を抱くようになり、長期的な関係性を築くことが可能になります。
この地道な一貫性の積み重ねこそが、強いブランドを育む上で不可欠な要素なのです。
メルマガにも力を入れているフォルクスワーゲン
デジタルコミュニケーションが多様化する現代においても、メールマガジンは顧客と直接的かつ継続的な関係を築くための重要なツールです。
フォルクスワーゲンは、このメールマガジンを単なる情報発信の手段としてだけでなく、顧客との感情的なつながりを深め、長期的な信頼関係を育むための戦略的なチャネルとして重視しています。
その取り組みの背景には、一方的な販売促進に終始するのではなく、顧客一人ひとりの状況や関心に寄り添ったコミュニケーションを通じて、ブランドへの愛着を深めてもらいたいという思想があります。
フォルクスワーゲンのメールマガジン戦略の特徴の一つとして考えられるのは、顧客データの活用に基づいたパーソナライゼーションの追求です。
例えば、過去の車両購入履歴や、定期点検の時期、あるいはウェブサイトでの行動履歴といった情報を基に、それぞれの顧客にとって最適なタイミングで、最も関心の高い情報を提供する試みがなされていると考えられます。
具体的には、新しいモデルのオーナーであれば、その車種の便利な機能紹介やメンテナンスのコツ、関連アクセサリーの情報などが届けられるかもしれません。
また、長年乗り続けている顧客に対しては、走行距離に応じたメンテナンスプランの提案や、最新モデルへの乗り換えを検討する上で役立つ比較情報、あるいはブランドの歴史や未来のビジョンに触れるストーリーなどが配信されることも想定されます。
またフォルクスワーゲンの商品を購入したことのないユーザーも、メルマガを受け取ることは可能です。実際に公式HPから登録してみると、こんなメルマガが届きました。
商品の購入には至っていないが興味を持っている人。つまり見込み顧客へ向けた内容となっています。
柔らかく親しみやすい印象のアイキャッチが魅力的ですね。埋め込まれた動画から、ブランドストーリーを知ることもできます。
2回目の配信では、大まかなフォルクスワーゲンの歴史がわかりやすい写真付きで紹介されています。
さらに3回目の配信では、「あなたにぴったりの一台をフォルクスワーゲンで」という件名で、具体的なラインナップがずらりと並びます。
1週間に1通という程良いペースで、読み手の気持ちに寄り添いながら、段階的にブランドの魅力が配信されています。
こうしたきめ細やかなアプローチは、受け手にとって「自分に関係のある情報だ」と感じさせやすく、開封率やクリック率の向上に繋がるだけでなく、ブランドからのメッセージに対する好感度を高めます。
まさしく、「人々に愛されるブランド」を目指すフォルクスワーゲンらしい戦略と言えますね!
まとめ
フォルクスワーゲンのブランドストーリーは、単なる自動車製造の歴史を超え、時代を反映し、巧みな戦略と揺るぎない哲学によって築き上げられてきました。
本記事では、その成功の秘訣を様々な角度から紐解いてきました。
フォルクスワーゲンのブランド構築の軌跡
| 歴史とブランドストーリーの重要性: 「国民車」構想から始まり、幾多の困難を乗り越え、世界中で愛されるブランドへと成長した背景には、常に「大衆のための車作り」という原点がありました。 広告革命「Think Small」: 製品の「小ささ」や「質素さ」を逆手に取り、正直さとユーモアで消費者の共感を獲得したこのキャンペーンは、広告史における金字塔であり、ブランドの個性を際立たせました。 ブランドの象徴「ビートルとゴルフ」: 単なる人気車種に留まらず、ブランドのDNAを体現し、時代を超えて愛され続けることで、フォルクスワーゲンの「人格」そのものを形成してきました。 変わらぬロゴと変化を恐れない姿勢: ロゴマークは、ブランドの核となる普遍的な価値を象徴しつつ、時代に合わせた変化も柔軟に受け入れ、ブランドの「信頼」と「革新」を表現しています。 |
現代におけるフォルクスワーゲンのブランド戦略
| 未来を見据えたビジョン「Mobility for Generations」: 電動化、自動運転、ソフトウェアを核とした持続可能で豊かな移動体験の提供を目指し、伝統的な自動車メーカーからモビリティのテック企業への変革を掲げています。 具体的な行動指針「NEW AUTO」戦略: EVへの本格移行、バッテリー技術・充電インフラへの投資、ソフトウェア開発能力の強化、MaaS分野への参入など、2030年に向けた明確なロードマップを示しています。 スローガンの進化:「Das Auto」から「Moving People Forward」へ: 製品中心から「人」を主役にしたブランドへと進化し、人々の生活を豊かにし、社会を前進させるツールとしての自動車の役割を追求しています。 サステナブルなブランドへの挑戦「Way to Zero」: 2050年までのカーボンニュートラル達成を目指し、生産プロセスからサプライチェーン全体に至る包括的な脱炭素化戦略を推進しています。 新しい「ピープルズカー」の形「ID.シリーズ」: 電気自動車の時代においても、サステナビリティ、革新的テクノロジー、ライフスタイルに寄り添うデザインを融合させ、「みんなのための車」を再定義しようとしています。 人の記憶に寄り添う「Love Brand」戦略: ブランドの歴史やヘリテージを活かしつつ、顧客一人ひとりの感情に寄り添うコミュニケーションを通じて、愛されるブランドとしての地位を確立しようとしています。具体的には、「フォルクスワーゲンマガジン」によるブランドストーリーの発信や、各店舗の「スタッフブログ」による親近感の醸成といった施策が見られます。 |
フォルクスワーゲン流ブランディング実践の3ステップ
| 1.「自社の原点」を見つめ直す: 企業独自の「らしさ」の源泉となる価値観を明確にし、ブランドの揺るぎない羅針盤とすることが重要です。 2.「物語」を語る: 製品やサービスに特別な意味を与え、顧客の感情に訴えかけるストーリーテリングによって、ブランドに人間味を与え、感情的な絆を築きます。 3.あらゆる接点で「一貫性」を保つ: ロゴ、広告、製品デザイン、接客応対など、顧客がブランドと触れる全てのタッチポイントで統一されたメッセージと世界観を提供し、信頼感を醸成します。 |
フォルクスワーゲンは、メールマガジンにおいても、顧客データの活用に基づいたパーソナライゼーションを追求し、顧客一人ひとりに寄り添った情報提供を行うことで、ブランドへの愛着を深める戦略をとっています。
これは、見込み顧客に対しても、段階的にブランドの魅力を伝え、親しみやすいコミュニケーションを通じて、長期的な関係構築を目指す姿勢の表れです。
フォルクスワーゲンの事例は、時代が変化しても揺るがないブランドの核を大切にしながら、革新を恐れず、そして何よりも顧客との信頼関係を第一に考えることの重要性を示しています。
これらの学びは、業界を問わず、全ての企業が愛され続けるブランドを構築するためのヒントとなるでしょう!
コンビーズメールはシンプルで続けやすいメルマガ!
弊社のメルマガサービス「コンビーズメール」は、初心者でも始めやすく、続けやすいことが強みです。一番の強みは他社にないシンプルさ。はじめてのメルマガに挑戦する方にぜひオススメのツールです!
| ・クレカ情報不要で無料トライアルが可能! ・使い方がとにかくシンプル! ・機能が必要最小限なので混乱しない! ・月額3,300円〜でリーズナブル! |
ぜひこの機会に、始めの一歩を踏み出しましょう!
この記事のライター
川上あおい
3児の母。川上サトシを支えつつ学んだことを活かし始めたハリネズミ。24時間、車を運転したことがある。

この記事の監修
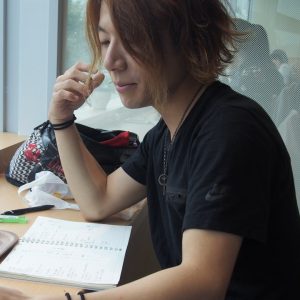
Webマーケティングに関するオススメ記事